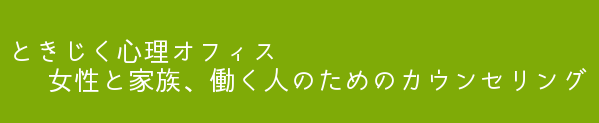統合失調症は人類にとって決して珍しいとはいえない発症頻度の精神疾患です。その発生機序にはまだ不明なことも多いですが、遺伝的な要因をはじめ各分野で研究がなされてきています。
疫学
遺伝的な研究は1991年のゴッテスマン,I.I.の報告が有名です。これによると、一卵性双生児のうちのどちらかが統合失調症だった場合、もう一人も発症する割合は50%近くであり、二卵性双生児だと10%台だったとされています。
ゴッテスマンは両親ともが統合失調症だった場合や片方のみの場合をはじめ、いくつかのパターンを調査しています。また、他の研究者も共通する遺伝要素などを含め、その要因を探ってきています。
ゴッテスマンのほかにもいくつか類似の研究はあり、数値にばらつきはあります。しかし、遺伝的な要因とともにおよそ半数は環境因が想定されるとみられています。
ドーパミン仮説
1951年、クロルプロマジンの作用に注目が集まり、脳内のドーパミンの代謝に影響を与える薬で症状が緩和する事実が明らかになります。そのため、この神経伝達物質が主要な役割を果たしてきているという「ドーパミン仮説」がスナイダー,S.らによって指摘されます。
しかし、1980年代からはこの説は主に「陽性症状」のみに当てはまり、「陰性症状」をうまく説明、治療できないことが指摘されるようになります。
1990年代に入り、脳部位にそれぞれドーパミンの過活動·低活動の箇所がみられる、というようにこの説は修正、再検討されるようになりました。
統合失調症の基礎データ
○生涯有病率
どの国、文化圏においても1%前後でみられています。
発症年代は10代半ば〜30代半ばに多くみられます。男女差はほとんどないといわれています。
回復へのとらえ方
統合失調症は完治ではなく、「寛解」という言葉を用いて回復を言い表しています。
かつては寛解率および予後は以下のようにいわれていました。
①病気になる以前にほぼ回復し、自立した社会生活が送れる
②症状が残るが、ある程度の自立した生活が可能
③重症化して長期の入院生活になる
現在では、以下の5パターンに分類されることもあります。
①完全に回復
②かなり改善、自立して社会生活ができる
③ある程度改善、生活支援が必要
④改善があまりみられない。療養施設での生活
⑤死亡
症状は年齢を経るごとに緩やかになる傾向があります。
現代では脳の研究が進み、統合失調症に関しての脳部位の影響や治療薬についても様々な角度から調査がなされてきています。