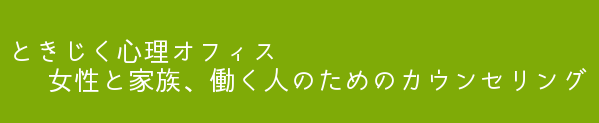ロールシャッハ・テストの生みの親であるロールシャッハ,H.は『精神診断学』を発表したのちの1922年に他界してしまいます。
幾つもの「スコアリングシステム」による混乱期
1930年代になってから、ロールシャッハ・テストは評価されるようになっていきます。ただし、彼の研究の意図や解釈などが明確に伝わっておらず、決定版がなかったことにより、研究者らの多くがその主張を受け入れ、賛同し、他方では疑問を呈しました。その結果として、1930~1950年代に5つもの学派が誕生しています。
その先駆けとして、1937年にアメリカで開発されたベック,S.J.とクロッパー,B.の2つのスコアリングシステムがあげられます。ベックは最初期の本格的な研究者であり、スイスに留学し、研究成果をアメリカに持ち帰ります。クロッパーはドイツ出身の研究者ですが、戦時中、アメリカへの亡命以前にスイスでユング,C.G.と研究に取り組む機会があり、ロールシャッハ・テストに触れたとされています。
しかし、ロールシャッハの主張を基盤とし、あくまでその考えに依拠するベックに対し、フロイト,S.やユングの精神分析的な観点に視座を置くクロッパーの現象学的アプローチとは考え方が相容れないものでした。
「包括システム」による統合
1974年にエクスナー,J.が発表した『包括システムの基礎と解釈の原理』はアメリカでのこうした状態に光明を投げかけます。ベックの助手であった彼は既に提唱されていた5種類のスコアリングシステムを比較分析します。しかし、それらはみな矛盾があるという結論に達しました。
エクスナーはそれらの課題を解決し、システムの標準化を目指すために膨大な実証的データによって、統合的なシステム・実施法の指針を打ち出します。各システムから明確な部分を抽出して作り上げたこの方式は「包括システム」と呼ばれることになります。
日本に渡ったロールシャッハ・テスト
その後もアメリカでは研究が続き、エクスナーの著書は版を重ねていきます。2006年、研究に30年を超える年月を捧げたエクスナーはこの世を去りました。しかし、ロールシャッハ・テストの研究は実践的に発展し、心理支援施設のなかで主流に用いられています。
日本でもロールシャッハ・テストは最早期の1930年頃から取り入れられています。先述のクロッパーのもとでは河合隼雄が学び、入門書を翻訳したほか、連綿と続く研究のなかで日本に合った見識も深められてきました。
国内の方式で主として取り入れられたものは片口安史による「片口式スコアリング」です。当方式は1974年に『心理診断法』、1987年に『新・心理診断法』が出版されています。国内の大学では名大式・阪大式なども有名です。
ロールシャッハ・テストはその性質上、歪曲を受けにくく、熟達したテスターによって無意識的な心理状態を深く探る手立てとなります。現在も心理士や精神科医によって実践され、学会や研修会、スーパービジョンといった様々な機会を通して研鑽が積まれています。