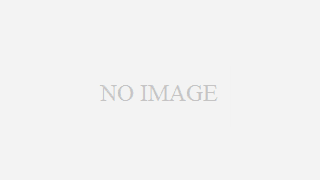 記事
記事 『グレート・マザー』ノイマン,E.
分析心理学の大家ノイマンの主著の1つ。2部構成であり、数ある元型のうちグレートマザーについて論じている。
Ⅰ部はグレートマザーをはじめとする主に女性の元型の心理学的機能および構造を論じる。母なるものの“包み込む”(「飲み込む」という...
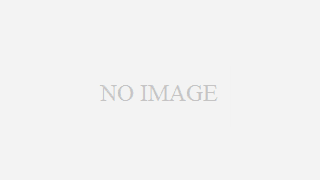 記事
記事 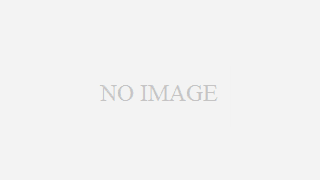 記事
記事 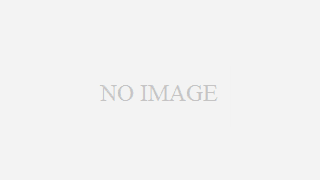 記事
記事 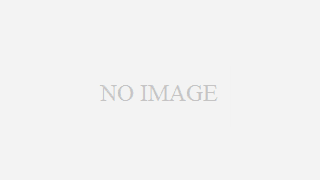 記事
記事 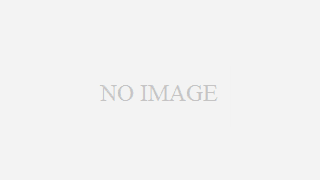 記事
記事 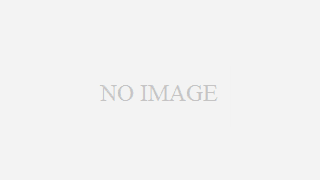 記事
記事 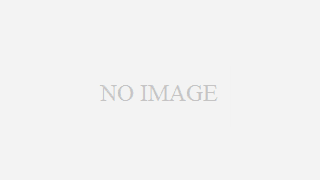 記事
記事 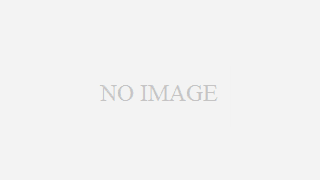 記事
記事 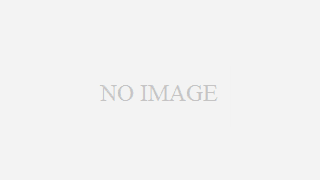 記事
記事 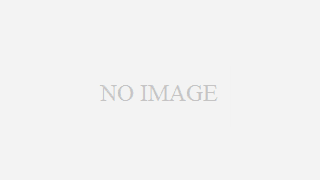 記事
記事