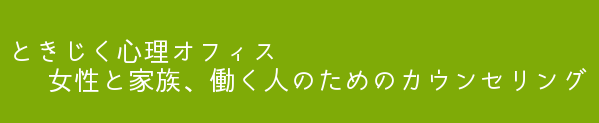ロールシャッハ・テストはスイスの精神科医ロールシャッハ,H.によって1921年に発表されました。
心理検査のなかでも「投影法」といった無意識のなかの感情や欲求を読みとる手法に位置づけられ、実践・研究が続けられています。
ロールシャッハによる開発
生みの親であるロールシャッハは1909年~1913年まで、スイスのミュンスターリンゲン精神病院で勤務医をしていました。この時期に考案されたロールシャッハ・テストは当初、個人が意識していない心の側面を明らかにするための研究用ツールでした。彼は精神科医ブロイラー,E.の弟子となり、ユング,C.G.の精神病理学も学びました。1911年頃、左右対称のインクの染みが精神疾患の診断に用いられないかという視点から研究に着手しますが、これは子どもの遊びから得た着想だったそうです。
公刊までの紆余曲折
40枚程のインクプロッドを用いるなかで、当初の図版は15枚だったそうですが、出版社に送ったものの全て断られてしまいます。その後、見直しを行って12枚となり、友人のモールゲンターラーが出版社にかけあってくれましたが、資金や会社の事情により、10枚となっています。加えて、できあがった図版はサイズが小さく、インクも濃淡が生じ、色も誤植となっていました。
ロールシャッハは不満を感じてはいたものの、のちになって、そうしてできてしまった図版に新たな可能性を見出したそうです。研究をやりなおし、この図版のデータをとり、1921年に『精神診断学』という書籍を公刊します。この本を通してロールシャッハ・テストが初めて世に発表されたことになります。彼はこの検査が色々な種類の精神疾患の診断に使えることを発見し、本のなかで主張しています。
しかし、彼はこの出版からわずか9ヶ月後、劇症の虫垂炎のために37歳の若さで他界してしまいました。
このように考案者の公刊翌年の死はありましたが、アメリカのベック,J.が当検査の研究を引き継ぎます。また、その助手であったエクスナー,E.がシステムの開発に大きな役割を果たします。結果的にロールシャッハの早期の死により、様々なシステムの開発や分析方法が考え出されていきました。
日本でも1930年代に導入されたロールシャッハ・テストは現在、医療機関などで心理状態や認知特性、パーソナリティーを把握するために用いられ、代表的な性格検査の1つとなっています。